目次
こんにちは、べびちぇる編集部のリカです。
はじめはおっぱいや哺乳瓶のミルクから水分を補給している赤ちゃん。マグやコップから自分で飲み物を飲めるようになるには、成長に応じた飲むトレーニングが必要です。
でも、赤ちゃんの飲むトレーニングについては、
「赤ちゃんの飲む練習はいつから始めたら良いの?」
「どんなふうに練習をしたら良いの?」
「わざわざ飲む練習をさせる必要はあるの?大きくなれば自然にできるようになるのでは?」
と、不安や疑問を持つママ・パパが多いもの。
そこで今回は、専門家である松本歯科大学の蓜島 弘之(はいしま ひろゆき)教授と、あすなろ小児歯科医院院長で歯学博士の佐野正之(さの まさゆき)先生のお二方に、赤ちゃんの飲む練習の進め方について、特に、赤ちゃんの口唇の発達促進の面からお話をしていただきました。
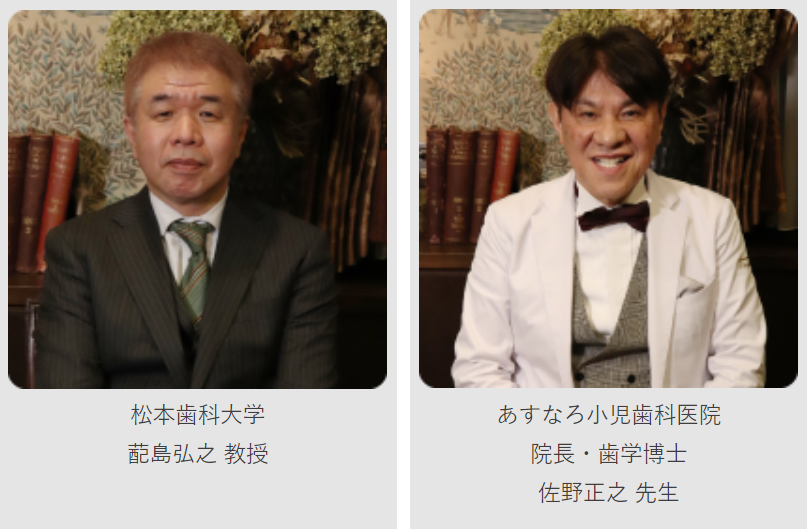
飲むトレーニングの重要性とは?
–蓜島教授、佐野先生、本日はよろしくお願いします。
早速ですが、赤ちゃんの飲むトレーニングはどうして重要なのでしょうか。
佐野先生:最近は虫歯が少なくなってきた一方、口が閉じられない、鼻で息が出来ない子どもたちがすごく増えてきましたね。
蓜島教授:そうですね。唇の力が弱くて上唇が富士山型になる、いわゆる「おちょぼ口」になっているお子さんが非常に多くなってきていますね。

富士山型の唇
赤ちゃんの歯というのは、舌で内側から押す力と唇で外側から押す力のバランスによりきれいに並ぶようになっているのですが、唇の力が弱いと歯を外側から押す力が弱くなり、歯の生え位置が広がってしまいます。
実は、赤ちゃんが乳首からおっぱいを吸い出すとき、赤ちゃんの舌は唇より前に伸びているのですが、長く乳首を使って飲み物を与えていると、
「舌が出る」→「唇が閉まらない」→「鼻呼吸ができず、口呼吸になる」
という状態となり、歯の生え位置に影響を与えますし、食べるときに悪い癖が出てきてしまう、といった恐れがあります。
そこで、唇を鍛えるため、飲むトレーニングが今非常に重要になっています。
佐野先生:唇と歯には、言葉をしゃべる、意思を伝えていく、様々な表情を表現する、といったとても大切な役割もありますね。
–飲むトレーニングで唇を鍛えることが、歯の生え位置や食べるときの癖、言葉や表情など様々なことにかかわっているとは驚きです。
口唇を鍛える方法とは?
–唇を鍛えるには、具体的にどうしたら良いのでしょうか。
蓜島教授:食べるトレーニングと飲むトレーニングを一緒に進めていくと良いですよ。
食べるトレーニング
蓜島教授:まず離乳食が始まったら、食べさせ方にポイントがあります。
離乳食は、赤ちゃんの口の中にこすりつけないようにしてください。

–ついつい、食べて欲しくてそうしてしまいがちですが・・・。唇の発達には良くないのですね。
蓜島教授:離乳食を口の中にこすりつけて入れてしまうと、唇を使わなくても食べ物が口の中に入りますので、唇を怠けさせることにつながってしまいます。
離乳食は口にこすりつけず、食べ物は赤ちゃん自身に唇や舌を使って口に含ませるようにしましょう。
飲むトレーニング
–飲むトレーニングはどのようにすれば良いでしょうか。
蓜島教授:いきなりマグで飲ませるのではなく、まずはスプーンで飲ませる練習をするのがおすすめです。
子供用のスプーンを使って、ひと口に飲み込む量を覚えさせましょう。
液体を与えるときはスプーンを横向きにするのがポイントで、液体が上唇に接する面積を大きくすると、口に入る物の性状・温度などを感じやすくなり、赤ちゃんが驚きにくくなります。

慣れてきたら、薄い蓮華(レンゲ)などを使って飲み物を与えます。
上唇と下唇を使い、連続して流れてくる飲み物を飲めるように練習しましょう。
このようにして飲み物に慣れさせて、飲む量を増やし、上唇の発達を促しましょう。
–マグの前にスプーンや蓮華を使った練習を行うと、マグにスムーズに移行できるんですね。知らないことばかりでした!
マグの練習の進め方は?
–マグで飲む練習をするときは、どのように進めれば良いでしょうか。
蓜島教授:マグで飲む練習をするときには、唇の発達に合わせて飲み口を選んであげるのが大切です。
5ヵ月頃から
蓜島教授:飲む練習は、離乳食の開始の時期(5ヵ月頃)からはじめると考えていただいて良いと思います。
最初は唇の力が弱いので、弱い力でも飲み口を包み込むことができるよう、哺乳瓶の乳首の形に近く、やや幅広でくわえやすい飲み口のマグが良いと思います。

トライ ストローレッスンマグ
こちらのマグはボトル中のストローの付け外しにより、子どもたちの飲む力の発達に応じて哺乳瓶のような上向きの飲み方から、下向きで吸って飲む飲み方へ移行することができます。

7ヵ月頃から
蓜島教授:7ヵ月頃からは口の機能が発達してきて、先が細いストローでも吸い上げが可能になってきますので、飲み口が細いタイプを使うといいでしょう。

トライ ストローマグ
–赤ちゃんにストロー飲みを教えるのに皆さんとても苦労されているようですが・・・。何か良い方法はないでしょうか。
蓜島教授:それには、このタイプのマグが適していると思います。

アクリア コップでマグ ストロータイプR
このマグは、フタのPUSHマークを押すことで、中の液体が少しだけ出てくるようになっています。

赤ちゃんははじめストローを見ても飲み物が出てくることが分かりません。そこでストローの先から飲み物が出てくることを体験学習してもらうことによって、ストローからは飲み物が出てくる、と覚えてもらうことができます。
こちらのマグは臨床でもよく使いますし、障害のあるお子さんにも非常に有効に使用させていただいています。
8ヵ月頃から
–コップ飲みは、どのように練習すれば良いでしょうか。
蓜島教授:大体8ヵ月くらいからコップへの移行を考えていいのではないかな、と思います。
赤ちゃんが哺乳瓶から液体を飲むときには最初乳首を前歯で挟んでいるのですが、だんだん前歯で挟まないで飲めるようになる頃ですね。併せて、離乳食を食べることで上唇の力がついてくる頃でもあります。
実はコップで飲み物を飲むときは、乳首やストローで飲むときと口の形、舌の使い方が全く異なります。
乳首やストローで飲む場合は、口全体で乳首やストローをくわえて吸い出すようにしますよね。
それに比べ、コップ飲みの場合は、上唇と下唇でコップのフチをキュッとくわえる形になります。
コップ飲みの練習には、このような飲み口のコップマグを使っていただくと良いですよ。

トライ コップレッスンマグ
–こちらのマグですが、飲み口がなんだか変わった形をしていますよね。

蓜島教授:こちらのマグは、中のプレートを押すと液体が出てくるような仕組みになっているんです。
これによって、上唇でしっかりとこのプレートを押してあげないと飲み物を飲むことができません。
コップ飲みでは、上唇と下唇を閉じ、正しい舌の位置を覚えるトレーニングが大事なのですが、こちらのコップレッスンマグは構造的に
- 上唇でプレートを押すと飲み物がでるので、唇を閉じるトレーニングができる。
- フチが壁の働きをして、舌が飛び出さず、正しい舌の位置を覚えられる。
- 液体が上唇に触れるので、どんな性状、量のものが口に入るか体験学習ができる。
といった特徴がありますので、効果的にトレーニングが出来るようになっています。
ストロー飲みとコップ飲みは全く異なる飲み方なので、それぞれトレーニングするのが良いと思いますよ。
飲むトレーニングの重要性とトレーニング方法のまとめ
飲むトレーニングの重要性と飲むトレーニングの進め方について、蓜島教授、佐野先生から教えていただいたことをまとめました。
■飲むトレーニングの重要性
- 唇の発達が未熟で、口が閉じられない(口でしか呼吸ができない)子どもが増加している。
- 舌と唇の力のバランスで歯の生え位置が決まってくるので、唇を鍛えることはとても大事。
- 食べる練習、飲む練習は離乳食初期頃からがおすすめ。口唇の発達を促すことができる。
- 唇の力の発達に合わせたステップ別マグで、徐々に鍛えていくことがおすすめ。
■飲むトレーニングの進め方
- マグで飲む練習をする前に、赤ちゃんの発達段階に応じてスプーン、レンゲなどを使って飲む練習をすると良い。
- 最初は、哺乳瓶の形状に近い広めのやわらか飲み口からはじめる。
- 唇の力が徐々に強くなり、細い飲み口でもくわえることができ、吸い込む力ができたころにストローを教える。
- コップ飲みのトレーニングでは、飲むときの舌の正しい位置を身につけさせる。
- ストロー飲みとコップ飲みは全く異なる飲み方なので、それぞれトレーニングすると良い。
–先生方、今日は大変ありがとうございました。
歯科大学教授×小児歯科医師×リッチェル共同開発の新しいマグも加わって、リッチェルの「トライ マグシリーズ」がさらにパワーアップしました!
リッチェルの「トライ マグシリーズ」は、成長やシーンに合わせて組み合わせ自在な、プラスαの機能がたくさんつまったステップアップできるマグシリーズです。
この「トライ マグシリーズ」に、さらに歯科大学教授×小児歯科医×リッチェルにて共同開発のマグが仲間入り!
シリーズを通して、ストロー飲みとコップ飲み、2つの飲み方がよりスムーズにトレーニングできるようになりました。
お子様の、あらゆる「飲む」シーンをサポートしてくれますよ。
赤ちゃんの発育にとても需要な役割がある、飲むトレーニング。
ぜひ、赤ちゃんの発達段階に応じて使えるトライマグシリーズで、親子で楽しくトレーニングしてみてくださいね。
詳しい情報は、こちらの特設ページをチェックしてみてくださいね。
飲むトレーニングの詳しい進め方とケアポイントの動画も公開中です。こちらもぜひご覧ください。























